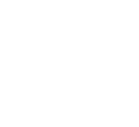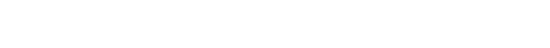Q&A
QUESTION & ANSWER
調査について
- 地盤調査は支持層から何mの深さまで実施すればよいか?
- 一般に基礎地盤に生じるすべり破壊は、補強土壁底面から壁高の1.5倍以内の深さに生じると考えられます。また、補強土壁の自重等による沈下の影響は、壁高の1.5~3倍以内の深さと考えられています。これらを目安として調査の範囲を判断してください。
部材について
- 壁面材にレリーフや岩のようなものは表面に加工可能ですか?
- 壁面材の表面には様々な加工が可能です。設計においては重量への影響を考慮する必要がある場合があります。詳細は協会にお問い合わせください。
- 笠コンクリート底部に使用するゴムプレート、笠コンクリート背面の発泡スチロールの規格を教えてください。
- ゴムプレート(硬度50)、発泡スチロール(発泡倍率50倍)を使用した実験結果に基づいて、以下の規格を標準としています。
■ゴムプレート- 硬質ゴムプレート
- 50%圧縮時の圧縮荷重が防護柵基礎反力の最大荷重であること
- 押出し法スチレンフォーム板(JIS A9521)
設計について
- 鋼製部材の腐食に関して、どの程度の耐用年数が見込まれていますか?
- 鋼製部材は、板厚あるいは直径に対して1mmの腐食代を考慮した有効断面積に基づいて許容引張り力を決定しています。通常の土中における鋼材の腐食速度が0.01mm/年程度とすると、1mmの腐食代を考慮することにより鋼製部材の耐用年数は100年見込めます。 特に厳しい腐食環境である場合や、仮設構造物として用いる場合には腐食代を適切に別途定める必要があります。
- 口径の大きい横断排水管の出口処理、壁面材に設けた排水孔の頻度・配置はどうすれば良いですか?
- 口径200mm以上の横断配水管を壁面材の前面に貫通させる場合、現場打ち鉄筋コンクリートに補強材を取付けることを推奨します。構造の詳細については協会にお問い合わせください。
- 水辺多数アンカーの透水係数の規定(k≧1.0×10-2cm/s)の根拠を教えてください。
- 水辺に適用した多数アンカー式補強土壁の挙動について調べた結果の概要は以下の報文に報告されています。
「水辺補強土壁に関する実物大実験(その1、2)、土木学会第65回年次学術講演概要集、2005.」
詳細については以下の共同研究報告書に報告されています。
「補強土擁壁の合理的な設計法に関する共同研究報告書(平成4年度~平成6年度): 財団法人 土木研究センター」に詳細な報告があります。
- 多数アンカー式補強土壁の地震時内部安定に用いる土圧の妥当性は調べられていますか?
- 実規模の振動台実験によると、補強領域内には拘束補強効果が発揮され、地震動が加わった場合においても補強領域は一体化して挙動することが確認されています。
実験の結果は以下の報文に報告されています。
「大型せん断土槽を用いた多数アンカー式補強土壁の実大振動台実験(その1、その2)、第35回地盤工学研究発表会、2000.」
- 浸水時のアンカープレートの引抜き強度特性について?
- アンカープレートの引抜き抵抗力に及ぼす浸水の影響は実験的に調べられています。摩擦系補強材が浸水の影響で引抜き抵抗力がひずみ軟化挙動を示すのに対して、アンカープレートの引抜き抵抗力はひずみ軟化せず、浸水後には抵抗力が回復する傾向が確認されています。実験結果の詳細については以下の報文に報告されています。
「浸水および排水の作用を受ける地盤内に設置した各種補強材の引抜き特性、土木学会第66回年次学術講演概要集、Ⅲ-059,2011.」
- 異なる強度特性の盛土を用いる際の主働土圧係数の考え方を教えてください?
- 盛土材の強度は作用土圧、および引抜き抵抗力に影響します。異なる強度特性の盛土材を用いる場合には、安全側の設計結果となるように小さい強度定数を用いて設計します。
- 両面壁のタイバーが他方のタイバー重なる場合、どのように配置すればよいでしょうか?
- 「橋台背面アプローチ部等の設計に関する共同研究(補強土壁の検証編)、https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1300.htm」において、「隣接する補強材と支圧プレートの寸法の 2 倍(2.0D)程度以上の離隔を確保する。なお、補強材の近接により引抜き力が増加することは抵抗が増大することに相当し、補強材の引抜き抵抗の観点では大きな問題にはならない。」とされています。支圧プレートの寸法の 2 倍(2.0D)程度未満の離隔アンカープレートの引抜き抵抗力の増大に対して、タイバーの破断に対して一定の余裕があり実用上問題ないと考えられます。
また、両面壁の補強材を緊結する場合について、「連結型については破壊形態等が異なる可能性があり、補強土壁の設計体系とは異なると いう整理とする。」とされています。
多数アンカー式補強土壁の補強材を緊結する両面壁については動的遠心模型実験で調べらており、補強材に作用する引張力は静止土圧係数を用いて算出することの妥当性が確認されており、以下の報文に報告されています。
「両面アンカー補強土壁を対象とした動的遠心模型実験-補強材引張力の比較-、令和2年度土木学会全国大会第75回年次学術講演会、Ⅲ-154,2020.」
- 底部付近のロックアンカー部のタイバーには、施工時に設計値以上の引張り力が作用することも考えられますが、ロックアンカー式の場合のタイバーに作用する設計引張り力はどのように考えますか。
- ロックアンカー部のタイバーには、土被りの小さい施工初期において主働土圧より大きな引張り力が作用する傾向が動態観測により確認されました。一方、土被りの増加に伴って、その引張り力は主働土圧と同程度の値となることも同じ動態観測から確認されています。したがって、施工完了後の安定性を評価する標準設計において、ロックアンカー部のタイバーに作用する引張り力は、主働土圧に基づいて設計してよいと考えられます。
【参考文献】
・「ロックアンカー式補強土壁の土圧の観測」:第38回地盤工学研究発表会、2003
- 重力式基礎の天端幅を1mとする理由と、壁面設置位置を重力式基礎天端の前面から0.4mとする理由を教えて下さい。
- 重力式基礎の天端幅は、壁面設置作業のためのスペースも考慮して設計することが望まれます。このため基本的に重力式基礎の天端幅を1m、壁面設置位置を重力式基礎天端の前面から0.4m(足場の最小幅)とすることとしておりますが、設計・施工条件を満足する場合で経済性などの影響から基本外形状が採用されることは考えられます。
- コーナーブロックを使用した場合、壁前面側に凸型のケースではコーナーブロックを挟んで両側のタイバーは、お互いの主働崩壊線から壁面側に敷設されるこがありますが、安定上問題はありませんか?また反対に凹型のケースでは、補強材が配置されない領域が広い範囲に及びますが、安定上問題はありませんか?
- 補強土壁の三次元的な影響は実務設計では検討されていないのが現状です。現時点では崩壊しようとする方向が異なる主働領域は同時に発生しないと考えて、検討対象の主働領域以外は安定していると仮定して二次元の設計検討を行っています。また、補強材に作用する引張力は、土圧が作用する壁面の面積に対して算出しており、安定について特に問題ないと考えられます。
- 補強土壁の地震動に対する変位量を求めたいのですが、算定式があれば教えて下さい。
- 補強土壁の変形を簡易的に評価する実務的な算定式は、いずれの補強土壁についても確立されていないのが現状です。
補強土壁の変形特性を評価しようとする場合、盛土材料の物性や補強効果を適切にモデル化して有限要素解析(FEM)などを適用することが考えられます。多数アンカー式補強土壁のFEMモデルについては協会にお問い合わせください。
- 補強土壁頂部に防護柵と側溝を隣接して設置する場合、どのように設置しますか?
- 補強土壁頂部に設置する防護柵の基礎と笠コンクリートを直結しない独立型とすることが望まれます。標準的な防護柵の設置例はマニュアル巻末の「付録-4 防護柵の設置例」を参照してください。
隣接して側溝を設ける場合は、標準的な防護柵基礎の形状ではなく、防護柵基礎の竪壁を高くすることもあります。ただし、常時・地震時・衝突時における防護柵基礎の安定と部材応力度の照査を実施しておくことが必要です。
- 防護柵基礎の設置に際して、ゴムプレートおよび発泡スチロールを設置する目的を教えてください。
- 防護柵を補強土の近傍に設置する場合、支柱を土中に埋め込む形式とするのが標準です。一方、隣接する構造物や用地制限によりやむを得ず補強土壁の頂部に設置する場合には、「防護柵の設置基準・同解説:(社)日本道路協会」、「道路土工-擁壁工指針:(社)日本道路協会」、「車両用防護柵 標準仕様・同解説:(社)日本道路協会」等を参考にして十分な検討が必要です。
補強土壁頂部の防護柵(例)では、防護柵基礎と笠コンクリートとの間にゴムプレートを設置するとともに、笠コンクリートの背面に発泡スチロールを設置することとなっています。ゴムプレートは防護柵基礎からの鉛直力を笠コンクリートに伝達させ、水平力は伝達させない目的で設置します。また発泡スチロールは、衝突による衝撃力の壁面材への影響を緩和するために設置します。
盛土材について
- 壁面材の背面に使う良質土は具体的に何を用いれば良いですか?
- 透水係数が1×10-3~1×10-2cm/s程度以上の良質な砕石、砂を用いるのが標準です。再生砕石については長期的な透水性能が確保できることを確認してください。
- トンネルズリを使用する場合、粗粒材料の締固め管理方法について教えて下さい。
- 密度管理が困難な岩砕や粒径の大きい粗粒材を盛土材として用いる場合、事前に試験施工を実施して、締固め機械、締固め回数、まき出し厚、施工含水比等について規定する工法規定によることを標準としています。
- 盛土材改良に関する擁壁工指針の記述について、フレキシブル性と透水性を確保した改良とする際の手法について教えてください。
- 低品質な盛土材を固化材により固めた場合には補強土壁の特性を損なうと考えられます。フレキシブル性と透水性を確保した土質改良の手法として固化破砕土とするのが一案となります。固化破砕土を多数アンカー式補強土壁に適用した事例は以下に報告されています。
「固化破砕土を盛土材とした多数アンカー式補強土壁工法の施工事例、土木学会第62回年次学術講演概要集、2002.」
実績について
- 多段積みの多数アンカー式補強土壁の事例はありますか?
- 多段積の多数アンカー式補強土壁は施工実績があり、「多数アンカー式補強土壁設計・施工マニュアル:(財)土木研究センター」では、安定検討の考え方が示されています。多段積事例の詳細については協会にお問い合わせ下さい。
- 多数アンカー式補強土壁を解体,再構築した事例がありますか?
- 解体、再構築した事例はあります。解体した部材の再利用,および解体歩掛については協会にお問い合わせください。